
京都の永観堂にて (1月6日撮影)
1月10日に、松屋銀座の「利休のかたちー継承されるデザインと心ー」展へツレを誘い出かけました。2人で出かける久しぶりの銀座です。
「東銀座」駅で降りると、来月の歌舞伎座のチケット予約を・・・とすぐに決まり、売り場へ寄ると、なんと上演中の寿・初春大歌舞伎の良席が空いていたのです。早速、某日昼の部のチケットを購入し、松屋銀座へ向かいました。
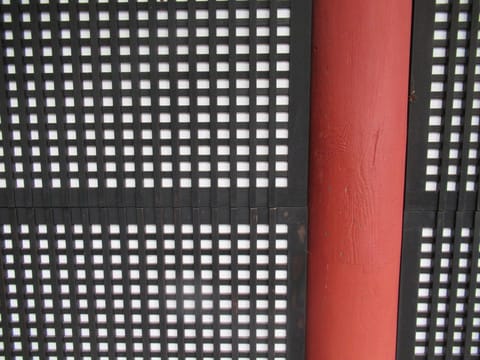
以後、感想などというものではなく、勝手な独り言です。
利休形(好み)と称される展示品を見ながら、私の数少ない茶道具の中に多くの「利休形」が含まれていることに改めて気づきました。
例えば、最初に購入した楽茶碗は長次郎「喝喰」の写しです。端正な形、カセタ黒釉薬、ヤットコの跡などがあるお気に入りです。
他にも桐木地丸卓、桐木地四方棚、木地釣瓶水指、旅箪笥、角不切折敷、黒塗小丸碗、朱塗引き杯、黒塗縁高、黒塗手燭などなど。
どれも木地や漆で黒く塗られたシンプルな印象のものばかりです。
展示もしかり、とても地味で控えめで・・・けれど長い年月を経て伝えらえてきた物の持つ、静謐な美しさに惹きつけられました。
茶道具における「利休形」とは「標準形」という意味ではないだろうか・・・という意見に頷きながらも、それとは違う感情、感覚が身体を駆け抜けていくのを感じます。
・・・それはまるで、道具たちからひそやかに発せられるささやきのようでした。その日はすいていて、ゆっくり展示品を鑑賞できたからかもしれません。
〇 赤楽茶碗 銘「白鷺」
長次郎作 安土桃山時代 16世紀 裏千家今日庵
2年前の東博でこの茶碗に出逢ってから2度目の出逢いですが、その時の繊細で素朴な印象とは一味違っていました。白鷺を思わせる白い繊細な縦線が前より濃く荒々しく(ライトの当て方のせいか?)、指跡でつけられたという解説を読み、長次郎の息づかいを間近に感じる思いでした。
この茶碗に魅せられて、茶碗の面影を慕って「小鷺」と名付けた白楽茶碗(染谷英明作)を愛用しています。
〇 黒楽茶碗 銘「万代屋黒」
長次郎作 安土桃山時代 16世紀 楽美術館
長次郎作の黒楽茶碗の中でも好きな茶碗の一つで、この茶碗に逢うと、京都の楽美術館を思い出します。ほの暗く静かな展示室で何度も何度もお逢いしました。
端正な形、静かで厳しい美しさを感じます。時代を経てカセタ黒釉薬がこの茶碗をより美しく魅力的にし、何度見ても見飽きません。主張があるようでもあり、無いようでもあり、使ってみたいです。
〇 湯の釜
与次郎作 安土桃山時代 16世紀 武者小路千家官休庵
釜好きなので、宗易の釜コーナーで釘付けに・・・・。
「湯の釜」は初めてのお出逢いでしたが、大きさと言い、魅力あふれる肩の形と言い、なんておおらかで素敵な釜なのだろう・・・と感動しました。最初に「湯の釜」を観たせいか、「阿弥陀堂釜」や「芦屋霰地真形(尾垂)釜」などがかすんでしまうほどでした。「湯の釜」という、これといった気の利いた名前がないのもゆかしいです。
〇 本手利休斗々屋茶碗
朝鮮 朝鮮時代 16世紀 藤田美術館
韓国で山清窯のミン・ヨンギ作の斗々屋茶碗を入手して以来、斗々屋茶碗の古作を見てみたいと思っていました。
この斗々屋茶碗は利休所持と伝わっているそうで、興味深く拝見しました。
斗々屋茶碗にはいろいろ特色があり、見込みが深いものは「本手ととや」、浅いものは「平ととや」と呼ばれています。「本手ととや」には高台がきっちりと削り出されている、釉薬の灰色部分と枇杷色部分がいろいろな景色を織りなすなどの特色があります。
しかし、「本手利休斗々屋茶碗」は釉薬の窯変はほとんど無く枇杷色が強く、高台が低いなど、おおらかで自由な作りになっている。それ故、静かで落ち着いた佇まいであることが利休の目にかなったのではないか・・・と解説にありました。
〇 利休形茶器 十二
三代中村宗哲作 江戸時代・18世紀 中村家
表千家七代如心斎が利休形茶器として制定し、三代中村宗哲が作った十二器が展示されていました。薬器、白粉解、下張、スンキリの形と名前が一致せず、茶桶(さつう)と面中次の違いなど、わかっていないことだらけに愕然とし、勉強不足を実感です。
〇 唐物丸壷茶入 利休丸壷
中国南宋~元時代・13~14世紀 香雪美術館
今回展示されていませんが、利休所持の大好きな茶入です。香雪美術館で不思議な出逢いがありました。ぜひ、丸壷茶入を見てほしいです。

「利休のかたち」展を拝見して、道具たちのひそやかなささやきに耳を傾けながら
「利休さんのデザインや心を深く考えながら、お茶事をしてみたい!」・・・とおもふ、懲りない茶事バカがいました(お道具もないのにねぇ~・・・影の声)









 、朝早く美容院で髪を結い(凄い余裕・・・)、古代紫色の紋付に金茶地唐花文の丸帯、帯締めは白で臨みました。身支度を調えると、中身や気持ちまでしゃんとして、活力が漲る気がします。
、朝早く美容院で髪を結い(凄い余裕・・・)、古代紫色の紋付に金茶地唐花文の丸帯、帯締めは白で臨みました。身支度を調えると、中身や気持ちまでしゃんとして、活力が漲る気がします。 難波津に 咲くやこの花 冬ごもり
難波津に 咲くやこの花 冬ごもり
 )。
)。

















 Oさんのメール(3月28日付)
Oさんのメール(3月28日付)






























 ・・・写真は時事通信フォト)
・・・写真は時事通信フォト)

















 暁庵先生へ
暁庵先生へ




 」
」





















 (夜に雷のため一時停電)
(夜に雷のため一時停電)

