
11月4日、京都在住の折、共に自主稽古に励んだ茶友Sさまの茶会にお招き頂きました。
(だいぶ時が経ってしまい記憶が朧ですが、書き留めたく・・・がんばります
 )
)「急なことですが、薄茶一服またはランチを御一緒にいかがですか?」
とメールを差し上げたところ快諾してくださって、京都在住のKMさんとTYさんをお誘いして伺わせて頂きました。
KMさんは大学時代の同級生の奥様、京都滞在の折にはしばしばこちらにお世話になっています。
TYさんは京都住まいの折、京都で初めてお友達になってくださった方です。
Sさまのメールによると1週間前に茶事を催すので、その跡見風で濃茶薄茶をさしあげたいとのことでした。
跡見の茶事は茶事七式の一つですが、未だ経験した事がありません。
どのようなご趣向の茶会かしら?・・・とても楽しみでした。

12時頃に玄関を開けると、侘びた大籠に生けられたススキが秋の野を思わせます。
我が家の威勢の良いススキに比べると、秋風になびく風情が京風のはんなりでした。
垂涎の李朝箪笥(バンダチ)が置かれた玄関の間で身支度を整え、懐かしい奥の待合へ。
京都を離れるとき、送別の茶会を催してくださったSさま、はや4年近くの歳月が過ぎてしまいました・・・。
待合の床に御軸があり、水面に映っている月の画のようです。
波が描かれているので海なのか湖なのか・・・月のさやけさを感じながら拝見しました。
それに、やんごとなき方々は空ではなく水面に映る月を愛でたとか・・・そんなお話も思い出します。
待合でご挨拶をして白湯を頂き、かわいらしい瓢弁当と吸い物をご亭主と一緒に頂戴しました。
私たちはのんびり味わって頂いたのですが、ご亭主の食べるのが早いこと・・・きっとお支度が気になっていたのでしょうね。
「お食事が済みましたら、どうぞ腰掛待合の方でお待ちください」

ここからが本格的な茶会となります。
待合の広間から庭へ出ると、腰掛待合があり、そこから外露地、枝折戸の向こうに蹲踞と内露地があり、その向こうに三畳上げ台目のステキな茶室があります。
腰掛待合で3人が待っていると、伽藍石のある露地の苔が露に濡れて青々と目に入ります。
折しもツワブキが満開でした。
腰掛待合に置かれた行李蓋の煙草盆、古伊万里の火入の灰形を拝見していると、ご亭主が現われ蹲踞の水を改めています。
枝折戸が開けられ、無言の挨拶を交わしました。
蹲踞で心身を清め、席入りしました。
床を拝見すると、淡々斎の穏やかな御筆で
「秋風一声雁」
床柱に籠花入が掛けられ、時候の花が・・う~ん?・・・思い出したら書きますね。
あとで籠花入は李朝の民具と伺いましたが、とてもステキでご亭主の李朝好みが窺えます。
炭手前がないので、「冠」香合(鵬雲斎お好み)が荘られていました。
(う~ん・・・水面に映る月、冠・・・光源氏または源氏物語のテーマかしら? それともお能のなにか?)

点前座には陶器の風炉に筒釜が掛けられていました。
陶器の風炉に見覚えが・・・韓国の陶芸家・全日根(故人)造の白磁の大ぶりな鉢です。
2014年葵祭の日、「川口美術」の片庇(かたひさし)の茶席で薄茶を点ててくださったご亭主を懐かしく思い出し、実はあの時から心惹かれる全日根さんの大鉢でした。
筋筒釜は大西浄林作とか。
大西浄林は大西家(江戸時代初期から京都・三条釜座において釜作を続ける釜師の家系、千家十職の一家)の初代です。
筋の入った筒釜はたっぷりとして力強く、古釜の魅力と存在感が溢れていました。
その横にこれまた個性的な四方水指、あとでゆっくり伺うことにしましょう。
 (つづく)
(つづく)ツワブキ咲く跡見の茶会・・・その2へつづく
















 オーネルさんのメール
オーネルさんのメール





















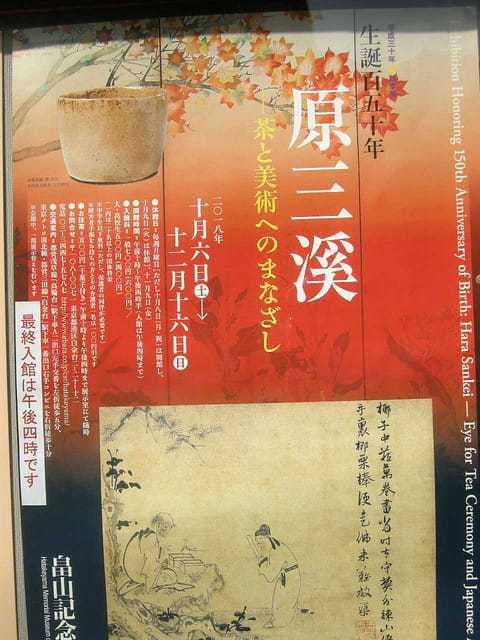









 )。
)。
















































 )
)




























